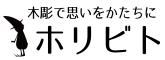字の彫り方 ~筋彫り、丸底彫り~

準備できましたら彫り進めていきましょう
筋彫り筋彫りは文字の輪郭をV字型に彫り、輪郭を浮かび上がらせる彫り方です。
今回はキワ刀12mm一本で彫ります。
まずは文字のすべての輪郭に切り込みをいれます ...
字の彫り方 ~準備~

お待ちかね、字を彫るシリーズのスタートです。
基本の詰め合わせ 「永」で練習書道で『永字八法(えいじはっぽう)』という言葉があります。これは、漢字の「永」には、トメ・ハネ・ハライなど楷書に必要な技法8種が全て含まれているこ ...
絶版本の宝庫 ~国立国会図書館デジタルコレクション~

国立国会図書館がデジタル化した資料は、オンラインで無料提供されており、
「国立国会図書館デジタルコレクション」で検索して利用できます。
会員登録しなくても
インターネット上で公開することについて問題がない ...作品サイズを決める目安

木彫作品の作る際にサイズを決める目安について書き記していきます。感覚的な部分もありますが、検討の一助になれば幸いです。
教室内で作ることを想定していますので、大きくてもリュックなどに入れて家と教室 ...
基礎を固めて道をひらく

学問、音楽、スポーツ、木彫、何事も最初の基礎固めが大切です。木彫は、木材と彫刻刀を揃えれば誰でも容易にスタートできますが、基礎を固めないまま次から次へと彫っても進歩しませんし、良い作品は生まれません。
教室入会後、精度の高 ...
文様の彫り方 その17 ~波~

波のっていくで
今回は次の下絵の波をできるだけシンプルに彫っていきますが、難易度高めです。自分なりのイメージ作りながら彫り進めることができなければ太刀打ちできないでしょう。
使用した刃物はキワ刀12mm、キワ刀 ...
文様の彫り方 その16 ~雲~

もこもこいくで
今回は次の下絵の雲をできるだけシンプルに彫っていきます。
上手くできましたら、さらに以下の下絵を透かして彫っていきましょう。
使用した刃物はキワ刀、浅丸刀で ...
文様の彫り方 その15 ~亀甲(きっこう)、矢絣(やがすり)~

今日はおなじみの亀甲(きっこう)と矢絣(やがすり)の彫り方を説明します。
亀甲(きっこう)は正六角形で構成された文様で、亀の甲羅に似ていることからその名が付けられました。
矢絣(やがすり)は矢羽(やばね)の形を ...
文様の彫り方 その14 ~市松(いちまつ)、三崩し(さんくずし)~

今日は「市松(いちまつ)」、「三崩し(さんくずし)」の彫り方を説明します。
「市松」は色違いの正方形を交互に並べた文様です。古くから「石畳(いしだたみ)」と呼ばれていましたが、江戸時代の歌舞伎役者の佐野川市松(さのがわ い ...
文様の彫り方 その13 ~菊菱(きくびし)、八重菊(やえぎく)~

今日は菊菱(きくびし)、八重菊(やえぎく)の彫り方を説明します。
菊菱(きくびし)は菊の花を菱形で構成したもので、八重菊(やえぎく)は花びらを何枚も重ねて八重咲きを表現したものです。
...