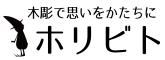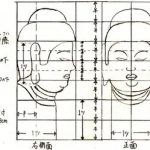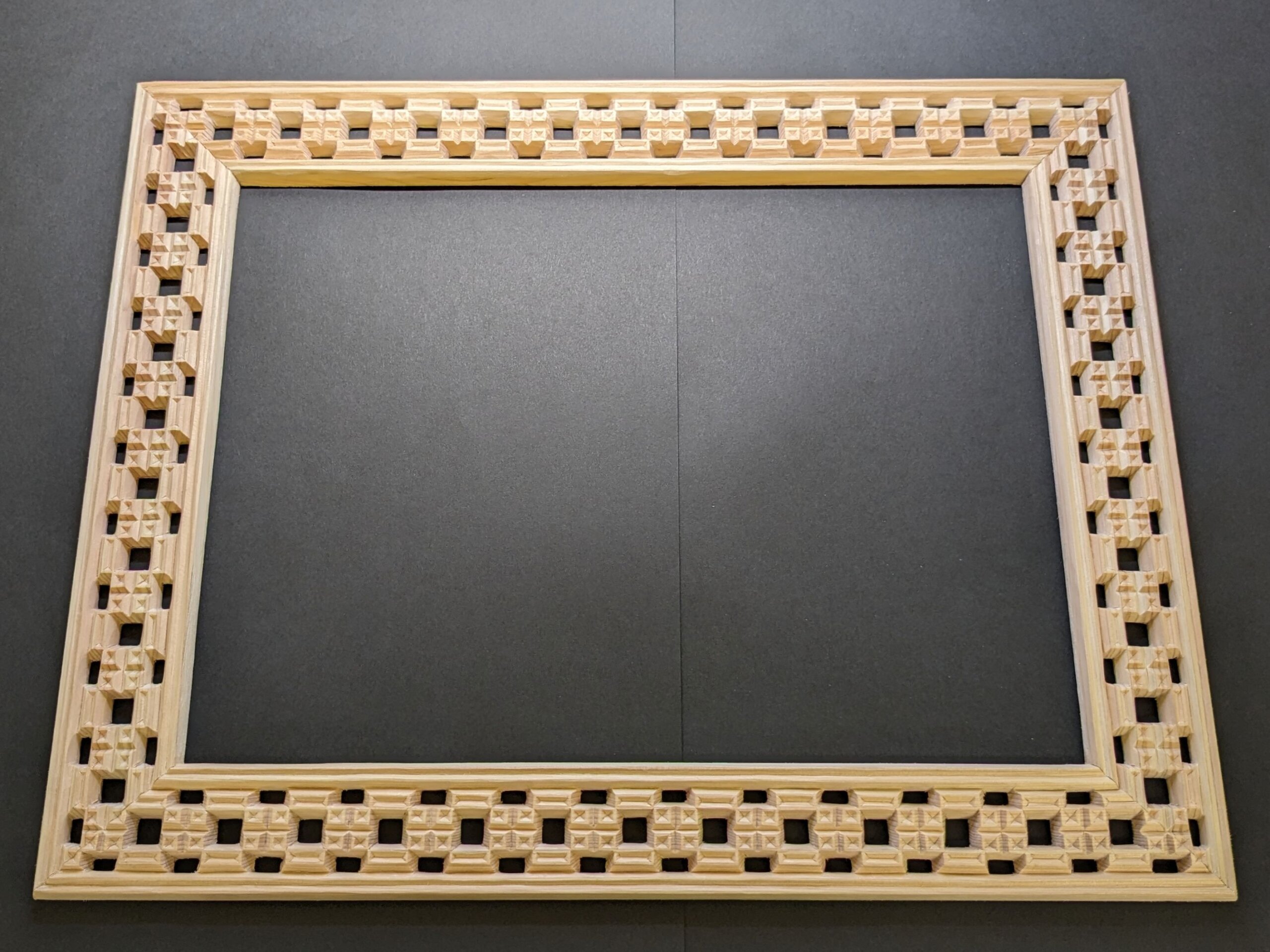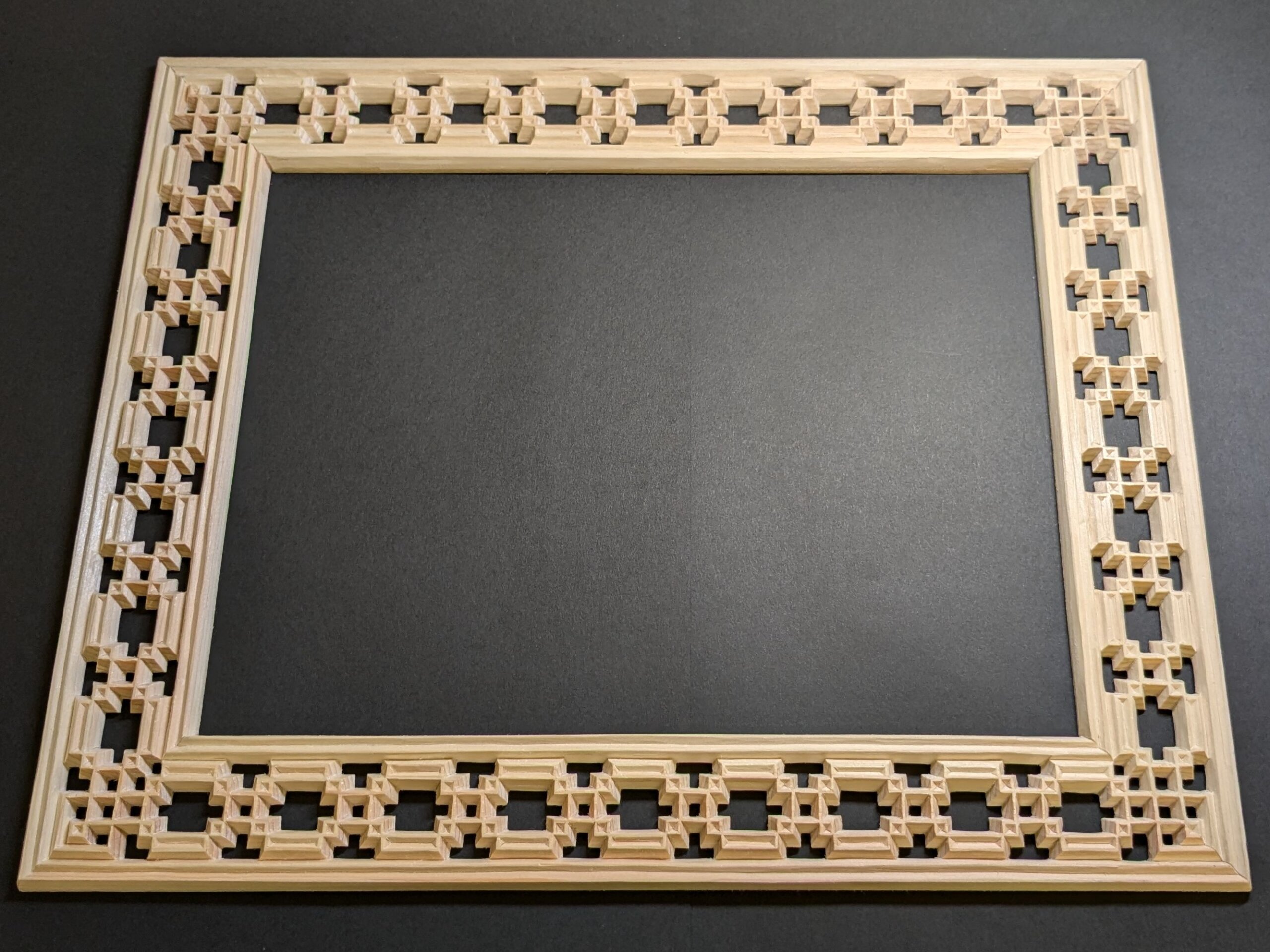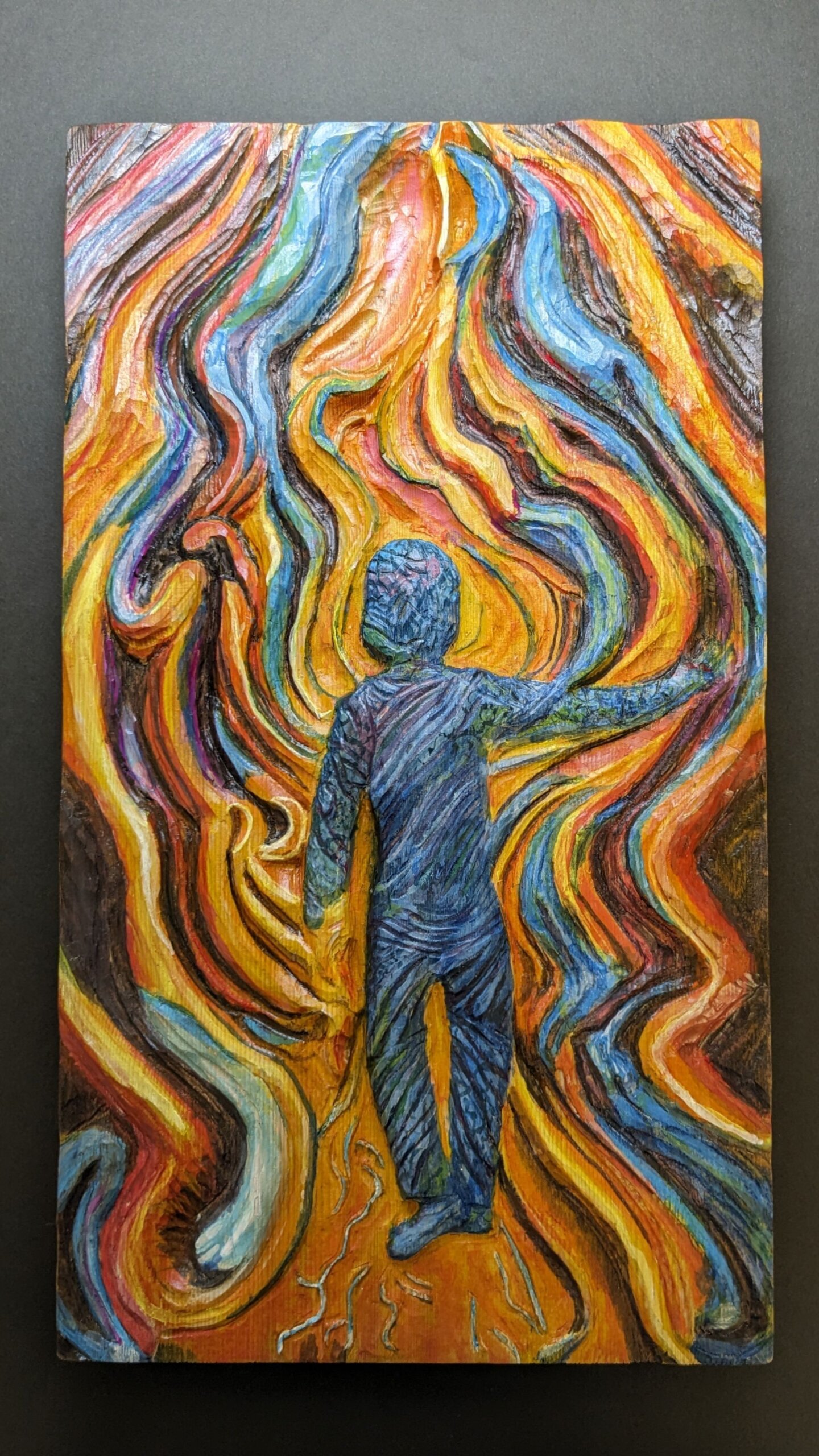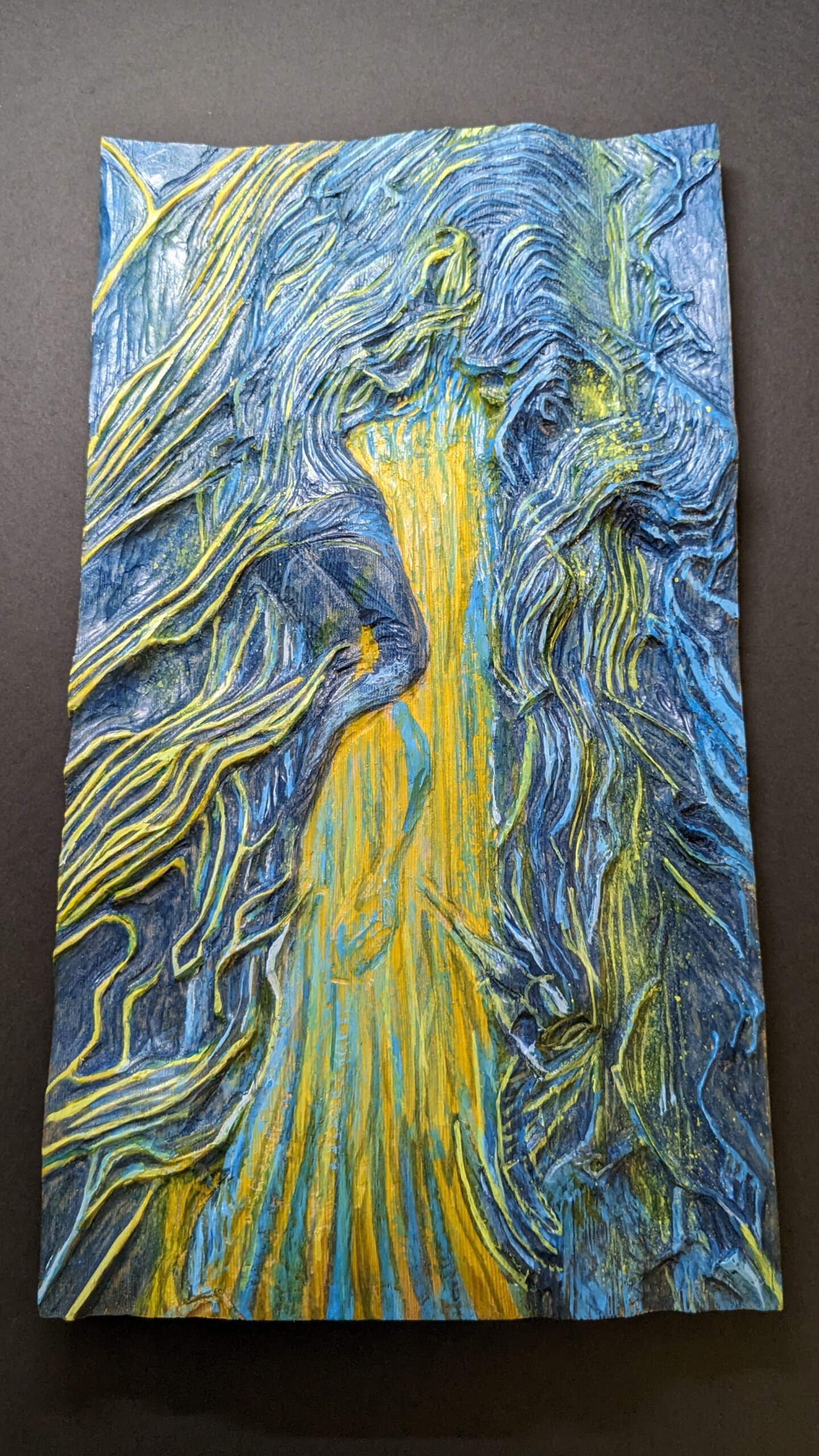舟形光背(透かし唐草)の彫り方 その1(舟形に彫る)
光背は、仏像の背面を飾っているもので、身体から放たれる光を表現したものです。
今回から数回に分けて、透かし唐草をあしらった舟形光背の彫り方を説明していきます。

舟形光背(透かし唐草)の下絵 
髪際と頭光が一致するように 
板材を用意する 
下絵に合わせて余計な部分をカット 
周縁部を湾曲させ舟形に 
舟形にしていく 
周縁部以外を厚めにしておく 
周縁部裏側のカーブ
①下絵を描く
まずは下絵を描きます。光背および仏像の赤丸のところが重なるように、彫り上げた立像の大きさに合わせて、描いた下絵を拡大または縮小印刷しましょう。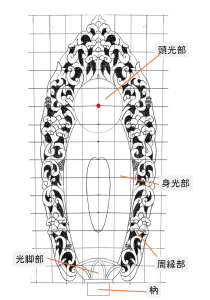

②板材を用意し、余計な部分をカットする

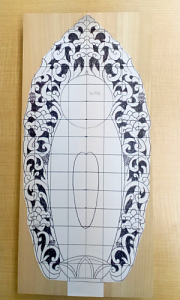
③舟形にしていく
のこぎりで取り除いたものを舟形に彫りこんでいきます。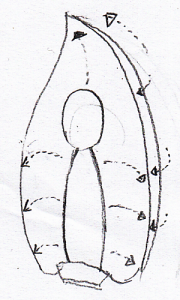



舟形光背(透かし唐草)の彫り方
- 舟形に彫る ←現在表示しているページ
- 唐草を彫る
- 光脚部、身光部、頭光部を彫る